|
|
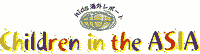 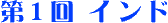 |
 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||
インドに何度か来て感じるのは、カーストも含めた階級社会の存在です。最初のころ驚いたのが、人を使うことと、人に使われることを、ある程度、当然のこととして受け止めていることです。これは他の多くのアジア諸国にもあてはまりますが、私個人の感想では、日本のような平等社会は、この地域ではほとんど例外だと言えると思います。日本でそれが完全 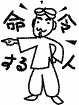 に実現されているとは言えませんが、少なくとも「平等であるべき」という価値観はあるでしょう。この点、日本から海外への駐在経験者の多くの方が、「人を使う」という経験がほとんどなく、使用人を雇うことの戸惑いを持たれたと思います。 に実現されているとは言えませんが、少なくとも「平等であるべき」という価値観はあるでしょう。この点、日本から海外への駐在経験者の多くの方が、「人を使う」という経験がほとんどなく、使用人を雇うことの戸惑いを持たれたと思います。さて、インドには裕福層のいる反面、大多数の貧困層の生活は大変です。今回は、ストリートチルドレン (Street Children) を取り上げます。直訳すれば「通りの子供」ですが、浮浪者の子供版です。大人に比べて大きな問題となるのが(1)親に捨てられたりして、自分の意思に関係なく路上で生活せざるを得ないこと。自分の意思で家を出た子供にも  家庭が原因による場合が多い。(2)麻薬や売春の危険にさらされていること。これはエイズの危険にもつながる。さらに、(3)学校へ行けず基礎教育が受けられない。したがって成人してからの就職がむずかしくなる。などがあります。 家庭が原因による場合が多い。(2)麻薬や売春の危険にさらされていること。これはエイズの危険にもつながる。さらに、(3)学校へ行けず基礎教育が受けられない。したがって成人してからの就職がむずかしくなる。などがあります。昨年(2000年)12月にデリーを訪れた際に、地元のスタッフと市内を歩きました。デリーは旧市街であるオールド・デリーと、イギリスの植民地時代に出来たニューデリーがあります。旧市街は、ごった返しており、通りを歩くと、物乞いをする子供や大人、子供連れの母親に会います。私自身が直接プロジェクトにかかわっているのではないのですが、今回、同行させてもらいました。 たいていのプロジェクトの場合、路上の子供の保護、施設に収容して健康や栄養面の処置、社会復帰のための教育が主な仕事です。何よりも子供たちとの対話が大事。話を続けるうちに、生い立ち、路上生活の理由を聞いていきます。絵を描き、歌を一緒に唄うなど、子供の興味を惹きつけることも大事です。物乞いをす  る子供には食べ物を買って、その場で食べさせます。というのは、大人に無理やり物乞いをさせられ、集めたお金をあとで「集金」されてしまうからです。今回もスーパーでクッキーやミルクを買って一緒に食べました。 る子供には食べ物を買って、その場で食べさせます。というのは、大人に無理やり物乞いをさせられ、集めたお金をあとで「集金」されてしまうからです。今回もスーパーでクッキーやミルクを買って一緒に食べました。ある程度心が打ち解けた時点で、施設への保護を進めます。施設のことを避難場所という意味でシェルター (shelter) と呼びます。ストリートチルドレンに対する教育で難しいのは、子供たちが転々としていることです。一度保護しても、数日で施設を出てしまい別の街へ移るため、続けて教育や栄養のケアをしてあげられません。ストリートチルドレンにとって、シェルターは「家」ではなく、各地を転々とする際の宿のようなも  のですから、なかなか一ヶ所に定住できないのが多くのケースです。特に、街中の刺激に慣れてしまうと、室内での生活に単調さを感じる子供が多く、彼らはまた街へ出てしまいます。 のですから、なかなか一ヶ所に定住できないのが多くのケースです。特に、街中の刺激に慣れてしまうと、室内での生活に単調さを感じる子供が多く、彼らはまた街へ出てしまいます。
|
「このシリーズ<Children in the ASIA>について」でもアジアの多様性を強調しましたが、その代表格がインドといって良いでしょう。これほど「混沌」という表現のあてはまる国はないのではないか、と思います。10億の人が住み、16の主要言語があります。ヒンズー教が主ですが、イスラム教、仏教、キリスト教徒もいます。貧富の差が極端に激しく、超金持ちもいれば、一日100円以下で生活する人の数も億単位です。 ************** インド人は良くしゃべります。その自己主張と押しの強さは、いつ相手の話を聞いているのかなと思うくらいです。そんなインドをネタにしたジョークをいくつか紹介します。 国際機関の職員:「地域会議の成功の秘訣は、いかにインド人を黙らせて日本人にものを言わせるかだ。」  旅行ガイド:日本では、バスに乗ると、「運転の邪魔になるので運転手に話しかけないで下さい」と表示してあります。一方、インドのバスの表示は、「運転手がしゃべりかけても、応えないで下さい。」とあります。 旅行ガイド:日本では、バスに乗ると、「運転の邪魔になるので運転手に話しかけないで下さい」と表示してあります。一方、インドのバスの表示は、「運転手がしゃべりかけても、応えないで下さい。」とあります。************** 最後に、インドにはまるパターンとは:「インドに着いた初日に、その汚さ、混雑に参ってしまって、すぐに逃げ出そうとする。でも気がついたらひどい下痢で全く体が動かない。しかたなく4-5日いると、徐々に慣れてきて、2週間もすると、その混沌さが快感に変わってくる。」 |
||||||||
| ▲TOP | |||||||||